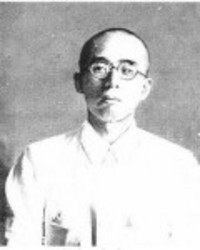一億の肩 / 轟の壕と島田知事 / 阿嘉島住民虐殺と食糧支配
米軍の動向
南進する米軍
Marines of the 8th Regiment, Second Division, on their way to the front on Okinawa, march across Naha airfield.
前線へ向けて那覇飛行場を行軍する第2海兵師団第8連隊(1945年6月16日)
八重岳 - 最後の追い込み
米軍にとって、玻名城の山を占領し、八重瀬岳の外郭を奪ってのちというものは、牛島中将の地下壕と米第24軍団とをへだてるものは、なだらかな高地台だけであった。捕虜によると、牛島中将の本部は、軍団の作戦区域内最南端にある巨大な珊瑚礁の岩山内にあった。この岩山は、テーブル型で、頂上は大体同じ高さ、岩肌がところどころむきだしに見えている。岩山の中には、グループになっているところもあり、そういうところは、一つの防壁となっていた。そのほか、あちこちに灌木や草むらに中から頭を出し、あたかも地面から生えているような岩があった。日本軍が2、3個の要塞をつくれるくらい大きな岩山があった。こういう大きな岩山が一つの八重瀬岳であり、また一つは与座岳で、第96師団作戦区域の北端にあるものだった。(496頁)
…与座岳は、…6月16日に陥落し、おなじ日に第17連隊と第32連隊は、153高地と115高地を占領した。それでも、日本軍が完全に敗れるまでには、もう一度、激しい戦闘の日を迎えなければならなかった。(497頁)
Men of 7th Division looking over the situation near Hill 153
153高地付近の状況を観察する第7師団の兵士
日本兵と民間人捕虜の収容
火炎放射器で掃討する。
沖縄南部の畑に接近する海兵隊員。音を聞きつけたのでそこに日本兵が隠れていると見ている。(1945年6月16日撮影)
Marines approach a field in southern Okinawa where they hear noises, suspecting Jap soldiers are hiding there.
サトウキビ畑に発煙手榴弾を投げ込み、日本兵が出てくるのを待つ海兵隊員。(1945年6月16日撮影)
Marines waiting for Japs to emerge from cane field, into which smoke grenades have been thrown.
壕で見つかった地元民と日本兵のグループ。地元民は営倉へ、兵士は捕虜収容所へ連れて行かれるまで(民間人収容所と捕虜収容所の)中間地点に集められた(1945年6月16日撮影)
Group of natives and a Jap soldier found in caves are brought to a center point, until they are taken back, the civilians to a stockade, the soldier a POW.
第32軍の動向
本土決戦 -「我に大陸作戦の利」
大本営はすでに「本土決戦」に切り替えた。
6月16日、糸満市に与座岳がアメリカ軍によって攻略。追い詰められる日本軍と住民達はさらに南へと追いやられていきます。沖縄が地獄絵図となっているこの日、本土では、海軍が臨時戦備会議を開き本土決戦に備え、各種航空機を3,500機そろえる整備計画を決定。また、この日付けの本土の新聞には『本土決戦、一億の肩に懸る 我に大陸作戦の利』として『本土決戦を成功させるためには、戦場に協力すべき一億国民の必死必勝の覚悟にかかっている』という記事が載りました。沖縄の実態を知らない本土の国民はこの言葉のふるいたったのでしょうか。しかし、地獄の真っ只中にいた沖縄の人々もまた、つい数ヶ月前までは、同じような記事を信じていました。
崩れゆく防衛線 - 竹槍部隊
牛島中将最後の軍隊は、首里戦場の瓦礫とともにくずれ去った。南へ撤退していった戦闘部隊、そして使役部隊の兵隊たちは、毎日千人ずつ餓死した。生き残ったものは、死ぬまで戦ったが、しかしそれは、沖縄南部の日本軍最後の砦めざして、荒れ狂うように進撃する米軍の前には、部隊間の共同戦線も張れず、防備らしい防備もできぬ、単なる兵の集団にすぎなかった。
司令部壕の食糧事情
今や軍司令部といえども、食糧の蓄えは十分でない。軍管理部長葛野中佐は、各人1日握り飯1個に制限してしまった。…若い人たちは、飢餓感を制しきれぬ。皆危険を承知の上で、夜になると洞窟を抜け出し、付近の畑から甘藷や砂糖黍を失敬してくる。ときには大豆などの獲物もある。…当番兵は、日が暮れると競って食糧探しに出かける。甘藷は小指大のものが多かったが、夜ふけってそっと持ってきてくれる茹でたての2つ3つが、実に美味である。
…砂糖黍も、軍司令官以下皆でよくかじった。司令官や、薬丸は鹿児島育ちで、かじりかたが上手だ。薬丸の手ほどきで私も直ぐ要領を呑み込んだ。…戦前、敵来攻後の沖縄の食糧問題が議題になった際、若い県の農事課長が、「沖縄はニューギニアなどとちがい、甘藷と砂糖黍があるから戦が始まっても心配はいりません」と主張したものだ。今や我々は、彼の予言通りの恩恵に浴しているのだ。
《「沖縄決戦 高級参謀の手記」(八原博通/中公文庫) 382-383頁より》
Marines look at dummy Japanese tank as dead Jap lies in foreground
偽装戦車に見入る海兵隊員。手前は日本人の死体(1945年6月16日撮影)
6月16、17日ごろ、混成旅団は与座、仲座の西端ならびに105高地付近において、旅団司令部を中心に残存の僅少な勇士らが細々と抗戦を続けているに過ぎない。
潔く105高地の花と散り 九段の杜に返り咲きせむ
と鈴木少将が、辞世を送ってこられたのはこのころのことである。
思い見よ!この10日あまりの間に混成旅団の正面に投入した兵力は6千を下らない。その多くが小銃、竹槍のような原始的兵器をもって4万トンの戦艦より撃ち出す40サンチ砲弾や、空を掩う敵の銃爆撃、幾百の戦車群、幾十万発と惜し気もなく撃ち込んでくる敵陸上砲に抗し、怨みを報いるに術なく、朝霧の如く消え去るさまは真に千秋の恨事である。
《「沖縄決戦 高級参謀の手記」(八原博通/中公文庫) 400頁より》
国吉(くによし・くにし): 歩兵第32連隊第1大隊(大隊長・伊東孝一大尉)
6月16日、敵は朝から伊東たちの壕に猛攻を加えてきた。友軍はもとより、大隊の麾下諸隊の状況も一切不明である。
島田叡知事 - 轟の壕から摩文仁へ移動
沖縄県庁: (沖縄県知事・島田叡)・沖縄県警察: (警察部長・荒井退造)
沖縄県の島田知事と荒井警察部長の一行は、6月3日以降、最後の県庁・警察壕となった真壁村伊敷集落にある自然壕「轟の壕」に辿り着いていた。6月7日、島田知事は警察部を含む沖縄県庁の解散を決定した。(投稿者注: 解散日に関しては、諸説) 知事は、兼ねてから最後は軍と共に行動を取ると考えていたことから、16日朝、摩文仁の司令部に向かう。同じ頃、銃剣などで武装した日本兵十数人が入り込み、壕の入り口付近を占拠し、住民の動きが封じられる。
…豊見城村に居た那覇署も、高嶺村に居た糸満署も、申し合わせたように移って来たが、それを追うように避難民の出入りも激しくなった。いきおい敵の偵察機が注目するようになり、海上の艦艇から砲撃されるようになって、壕内外で死傷者が出始めた。食糧難の避難民は、夜になると壕外の畑へイモやサトウキビを取りに出掛けたが、これも狙われた。
そんなある日、陸軍の衛生隊の一団14、5人がなだれ込んだ。入ってくるなり傍若無人の振る舞いで、包帯交換を頼みに来た他部隊の負傷兵を追い返す冷淡さとは裏腹に、看護婦とは思えない連れの女性には、やけに親切だった。その様子を苦々しげに見ていた島田知事は、吸殻入れにしていた空缶をキセルで不機嫌そうに叩いていたという。「軍医殿」と呼ばれた准尉は「戦場に役人や警察官なんか要らない。この壕は野戦病院として使うから立ち退け」と言い放った。隈崎が「我々は軍司令部から『与座岳以南で県民指導に当たれ』との指示を受け、ここに居る。軍司令部の指令書があれば、いつでも壕を譲る」と反撃すると効果てき面。翌朝、…この一団は姿を消していた。(377頁)
こんな状況の中で島田は、軍司令部と共に摩文仁の壕に入っていた毎日新聞の野村那覇支局長へ使者を送った。(378頁)
野村那覇支局長の記録:
〈島田さんから伝令が来て〝会いたい〟といって来た。早速、真壁(伊敷の轟の壕)に島田さんを訪ねたところ、〝やはり自分は軍司令官と最後の行動をとりたい。摩文仁へ案内してほしい〟ということであった。翌日の未明、島田さんを案内して摩文仁の壕に牛島軍司令官と長参謀長を訪ね、そのまま島田さんはすぐ近くの軍医部壕に入った。…〉(378頁)
《「沖縄の島守 内務閣僚かく戦えり」(田村洋三/中央公論新社) 377、378頁より》
沖縄県知事 島田叡(しまだ・あきら)
伊敷の「轟の壕」を出た島田知事は、摩文仁の司令部壕を経由し、軍司令部の壕に身を寄せた。
警護官の回想:
「あの日は夜明けと共に、轟の壕を出ました。米軍の艦砲射撃が本格的になる午前7時までに行き着こうというわけです。轟の壕がある伊敷の丘陵を南へ突っ切り、古波蔵集落の東端をかすめて糸洲ー伊原ー米須ー小渡(現在の大度)ー摩文仁へと、丘陵地帯の山裾を拾って歩きました。道中は至る所、電線が垂れ下がり、県民や兵士の遺体が累々と横たわっていました。その一体、一体に長官は手を合わせておられた。少しやつれてはおられたが、動作は相変わらず機敏であられたですねえ。摩文仁では先ず、軍司令部の壕を訪問されました」(389頁)
「知事さんが軍司令部壕に入られ、私たちが表で待っていた時間は15、6分でした」(390頁)
《「沖縄の島守 内務閣僚かく戦えり」(田村洋三/中央公論新社) 388、389、390頁より》
軍医部壕の薬剤中尉の証言:
「島田さんに初めてお会いしたのは昭和20年の2月上旬、着任されてまだ1週間くらいの時でしたが、今度の知事は死ぬ覚悟で来た、大した男だ、といううわさが軍司令部内にもとどろいていましてね。会った第一印象も、その通りでした。4か月ぶりに軍医部の壕で再会した時、司令部壕の方が広くて堅固なのに、なぜ狭くて貧弱なこの壕へ来られたのかな、と不思議に思いましてね、私、島田さんに直接、聞いたんです。すると『牛島司令官が、こちらへ行け、とおっしゃったので参りました』と言われた。
それ以上の理由はご自身では話されなかったが、戦後、…高級参謀の八原さんを…訪ねた時、改めて聞きました。それによると、島田さんは司令部壕に牛島司令官と長参謀長を訪ねた時、『最後の行動を共にさせていただきたいので、この壕に居らせてほしい』と頼まれたそうです。ところが、司令官は『自決するのは我々だけでよろしい。知事は行政官で、戦闘員ではないのだから、ここで死ぬ必要はありません』と言われた。司令官としては島田さんに軍司令部壕に居てもらうと、危機が迫った時、自決しかねないと思われたようで、軍医部の壕に入るよう言われたのです」
《「沖縄の島守 内務閣僚かく戦えり」(田村洋三/中央公論新社) 390-391頁より》
そのとき、住民は・・・
阿嘉島 - 住民虐殺と朝鮮人軍夫の虐待
海上挺進第2戦隊 (隊長: 野田義彦) - 阿嘉島・慶留間島
米軍に一時捕虜となった後藤松雄・タキエ夫妻がスパイとして処刑された。米軍の記録した当時のフィルムに米軍捕虜となったときの後藤夫婦の映像が残されていた。
事件が起ったのはそれからずっと後になってからで、たぶん六月にはいっていたと思います。… 私らはそれだけで、銃殺にもならずに杉山に帰されたんですが、その翌日ですよ、爺さんと婆さんがひっぱってこられたのは。… 次の日、二人はまた本部に呼びだされて、そのまま帰ってきませんでした。その晩のうちに二人の遺体がみつかりました。道のすぐ側に首だけ土に埋められて、体は外にでていたからすぐみつかったわけです。爺さんは軍刀で首を斬られていました。婆さんは銃剣で刺し殺されていました。断った兵隊の名前もわかっています。
餓死する朝鮮人軍夫
私が医務室にいる時、よく朝鮮人の死体が運ばれてきました。検視をするわけですが、見なくても分かりましたよ。みんな骨と皮だけになってしまって、明らかに餓死です。 壕の中ではろくに食料もやらなかったようです。これらの朝鮮人の中から米を盗んで食ったとかで十数名が銃殺になったと聞いています。
それほど飢えていましたが、サトウキビといって、それを壕の中で一つでも食べられれば、お腹が一杯になります。… 食べ物で差別されることほど悲しいことはないんです。… 日本人の下で働いていたときは、本当にお腹が空いていたんです。1日、家で、1升分のご飯を食べなければならないのに、3合、1日に3合。それも定量を全部配ればいいんだけど、食糧係の人が(私たち分まで)自分たちで食べてしまい、1合にも満たない米しか配給しませんでした。日本人はそれほどひどかったんです。
軍に管理される住民の食糧
農耕班は年寄りから子供まで含み、部落民が山に逃げる前に植えつけたものを夜になってから取りに行く仕事で、漁撈班は海にいって貝や魚を取ってくる仕事であった。 部落民は自分たちの食料は、探してきて兵隊に渡したぶんから分けてもらうようになっていました。しかしそれではあまりにも少ないので、後には泥棒までする人が出てきたり、どうにもならない人達は、周囲に生えている草の葉や茎を食べたり、夜になるのを待って海辺に行き、流れてくる果物や甲板を拾って食べなければいけなかった。万が一、自分の畑だからと芋一つとろうものならものすごい罰が加えられました。これは軍民問わずなされたもので、死刑にまでされました。
私たちの場合は炊事班であったため食糧には不足せず、残り物をもらって家族や親戚に持って行ってやった。しかし部落民から不平がでてからは長続きしなかった。でも時々配給の配給があったし、自分たちで炊事をするので食事に困ることは全然なかった。部落民は畑からではないにしても桑の葉1枚とることも禁じられ、兵隊でも階級の低いのは勝手に食べることはできなかった。そして食料難も山場に来た時、2/3近くの部落民がアメリカーのもとに逃亡して行った。その中には何人かの日本兵も混ざっていました。
ある兵長の部下が食料を黙って食べたという理由で大怪我をしてやっと退院できたこの兵長が死刑された例があります。いよいよ兵長が死刑になる日が来た時、彼の上司の中尉が、「別の隊長の部下からは死刑しないで自分の部下を死刑にするということは、日本魂を持っているはずの兵隊が自分個人に恨みを持っていることだ」と、アメリカ兵のもとへ逃亡してしまった。
子供が生まれて15日目には待ってましたとばかりに早速お芋を盗みに行きました。私の他に二人一緒だったので大きな袋のいっぱい取って頭に担いできました。ところが途中、軍の監視に見つかってしまい、散々叱られる結果になってしまいました。私は、子供が生まれたばかりで今まで何も食べていないから、と無理にお願いしてやっと許してもらいました。ところがもう一人の人は、前にも確かに盗んでいったということで、散々に殴られてしまった。実はこの人は初めてだが、以前にこの人にそっくりのおばさんが何度か捕まっていたので同じ人だと思ってやったのです。
部落の人たちはみんなそのような目にあい、殴る蹴るの暴行をうけた人が多かった。しかし軍はみんな同じように暴行を加えたかと言うとそうではないです。部落民にはいつも軍は平等だ、と言っているくせに、実は知っている人達はいつも見逃していました。食料だけではない、川の水も勝手に飲んだり、洗濯してはいけないという事で、いつも監視の目が厳しくて私たちなど到底入れてもらえなかったです。ところが軍の知り合いの人達は自由に水を使用していました。彼らは私たちには、お山の産湯にする水さえくれなかったぐらいであるのに。その頃から私たちは軍に不信を抱き、アメリカ兵よりもこわくなっていました。
摩文仁に追われる避難民
【沖縄戦の絵】「家族を守ろうとした父」
昭和20年6月、砲弾のさく裂する中、母に手を引かれ那覇市首里から糸満市摩文仁に向けて避難した。壕という壕は避難者であふれ、ようやく石を簡単に積み上げ、上にサトウキビを置いた豚小屋を見つけ、中に入った。20人ほどが身を寄せ合っていた。しばらくして隣の豚小屋にいた日本兵が腰を低くして逃げていくのが見えたその時、戦車で迫ってきた米軍が日本兵めがけて豚小屋に無数の手榴弾を投げ込んだ。豚小屋も攻撃されて死者が出た。家族や小屋の人たちを守ろうと、病弱だった父親が両手をあげて外に出て行ったが銃で撃たれた。ひん死の重傷と悟ったのか、手榴弾で「自決」した。銃撃と手榴弾で両親ときょうだい4人、それに小屋の人たちの命が一瞬にして奪われ、姉と自分だけが生き残った。亡くなった家族を思い、収容所で来る日も来る日も泣いていた。「戦争のことは忘れたことは無いが、語りたくもなかった。しかし平和の大切さを若い人に感じてほしいと思って、幼いころの記憶をたぐって絵にした」
Natives of Southern Okinawa are brought to a place of safety after our quick sweep behind Naha. They pass a sea wall right across Senaga Shima. Marines of 6th Division are guiding them.
那覇が米軍に攻撃された後、南部の沖縄人は安全な場所へと移動させられた。瀬長島の真向かいにある防波堤を横切る。第6海兵師団が案内する(1945年6月16日撮影)(投稿者註: リンク先の和訳に投稿者が加筆)
米国海兵隊: Marine stand guard as Okinawans dig grave for their dead. Many of them died from starvation and lack of medical treatment, from Japs.
死者の墓を掘る地元民を見守る海兵隊員。死因の大半は日本軍から食糧や適切な治療を受けられなかったことによる 1945年 6月16日
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■